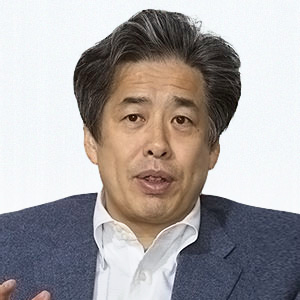2024年5月13日(月)更新
アントニオ猪木vsビル・ロビンソン。
濃密にしてシリアスな一夜限りの夢

アントニオ猪木が、恩師である力道山の十三回忌興行に参加しなかった理由については、前回述べました。十三回忌興行が開催された1975年12月11日は、猪木がビル・ロビンソンとNWF世界戦を行った日でもあります。舞台は前者が日本武道館、後者がそこから4キロ東の蔵前国技館。体が二つない限り、十三回忌興行に参加するのは不可能です。しかも先に決まっていたのはロビンソン戦です。<(十三回忌興行を)後から発表しておいて、先に発表したロビンソン戦をやめろというのは横車以外の何物でもない>(『論証アントニオ猪木』日本スポーツ出版社)という猪木の主張は、極めて筋の通ったものでした。
テーズとゴッチ
アントニオ猪木というレスラーは、いくつもの顔を持っています。現役のボクシング世界ヘビー級王者モハメド・アリ戦で見せた天性の格闘家としての顔、タイガー・ジェット・シン戦で見せた“ケンカ屋”としての顔、あるいはドリー・ファンク・ジュニア戦で見せた稀代のテクニシャンとしての顔……。このロビンソン戦でも猪木はテクニシャンとしての顔を惜しげもなく披露します。だがドリーのアメリカンスタイルに対し、ロビンソンのベースはヨーロピアンスタイル。どんなスタイルにでも対応できるのが猪木の非凡なところです。
この試合は60分3本勝負で行なわれました。リングを格調高い雰囲気に染め上げたのは、2人の立ち合い人でした。“鉄人”ルー・テーズと“神様”カール・ゴッチ。しかもレフェリーは、名レフェリーの誉れ高いレッドシューズ・ドゥーガン。こうした顔触れをプロレスファンは恍惚としてながめたものです。
戦う前、猪木はこう語っていました。
<よく、ロビンソンのスープレックスをどう封じるか、どう切り返すか、どのポイントでバックドロップを仕掛けるか、なんて、人に聞かれるんですがね。まったくそれはその時の臨機応変……0・何秒のスピードと変化、テクニックの勝負になったら、その時の反射神経、動物的なカンだけがものをいうのであって、あらかじめたてた作戦なんか通用しない。自分のコンディションをベストにし、反射神経で勝負する、それしかいえないですよ>(同前)
果たして、その通りの展開となりました。
年齢は猪木32歳。ロビンソン37歳。体を見るとロビンソンは競馬で言うところの“重め残り”のように映りました。
逆に言えば、ウェートの分だけパワーで上回るロビンソンは、立ち上がりから万力のようなヘッドロックで猪木を締め上げ、さらにはフィンガーロックなども繰り出します。「キャッチ・アズ・キャン」なら、オレの方が上だぞ、というプライドが垣間見えました。
60分決着つかず
しかし、ゴッチから基本を叩き込まれた猪木も負けてはいません。ネックロックでしつこくロビンソンの首を攻め上げ、スタミナを奪いにかかります。コンディション的には猪木に一日の長があるようでした。
地味ながら手に汗握る展開を経て、ロビンソンが試合を動かします。ロープ際のサイドスープレックスで猪木を場外に叩き落したのです。試合にアクセントを付けたかったのでしょう。
スタミナを温存したいロビンソンはグラウンド戦に持ち込み、アームシザースなどで猪木の左腕を攻めます。攻めながら休むあたりは、さすがに試合巧者です。
これを切り返した猪木、おはこのインディアンデスロックで逆襲に転じます。
先に大技を披露したのはロビンソンでした。ワンハンドバックブリーカーで、猪木の腰にダメージを与えます。さらにはボストンクラブに移行し、徹底して猪木の腰を攻めます。こうした攻撃の一貫性は、まるで“肉体のチェス”のようです。
立ち技あり、グラウンドでの攻防あり。2人とも引き出しの中の武器は無尽蔵です。どちらが先に1本目を取るのか。
先制フォールは40分すぎ。電光石火の逆さ抑え込みでロビンソンが猪木にスリーカウントを聞かせました。
いよいよ残り17分。猪木はもう攻めるしかありません。場外からリングに戻ったロビンソンにブレーンバスター、バックドロップを見舞いますが、とどめを刺すには到りません。
ガス欠寸前のロビンソンはそれでもダブルアームスープレックスを決め、千両役者ぶりを発揮します。
残り1分を切り、コーナーでもつれた際に猪木が繰り出したのが起死回生の卍固めでした。たまらずロビンソン、ギブアップ。残り30秒では決着がつかず、試合は1対1のドローに終わりました。濃密にしてシリアスな60分間でした。
猪木とロビンソンが戦ったのは、後にも先にも、この一度だけです。今になって思います。一夜限りの夢でよかったと……。

二宮清純