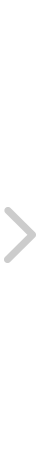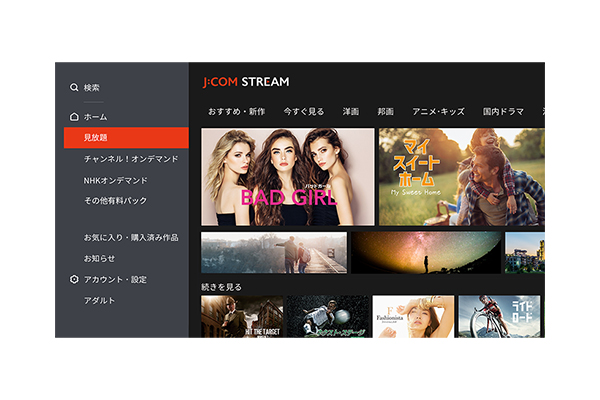声優・佐藤拓也
ロングインタビュー #2
演じるキャラから「合ってるよ」と
言ってもらえるような役作りがしたい
2024年7月26日更新
SATOLONG
INTERVIEW
『キャプテン翼』の日向小次郎や『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』のシーザー・A・ツェペリなどの往年の名キャラクターの熱演をはじめ、『憂国のモリアーティ』のアルバート・ジェームズ・モリアーティ、『アイドリッシュセブン』の十龍之介、『刀剣乱舞』シリーズでは燭台切光忠と江雪左文字の二役など、アニメ・ゲーム・吹き替えなど数々の人気作品に縦横無尽に出演する声優・佐藤拓也さん。「この世界以外に興味が湧かなかった」と一途に声優の道を志し続けてきましたが、人気声優となった今でもその熱は変わらず。「素敵な人たちに囲まれて、マイク前に立てることが幸せ」だと話します。このインタビューでは全3回にわたって、その軌跡と出演作品に対する思いをひもときながら、声優・佐藤拓也の原点と信念に迫ります。
先輩の背中に憧れた、声優としての原体験

――“声優としての転機”というと、佐藤さんご自身はいつ訪れたと感じていますか?
佐藤:僕自身、最初はアニメがやりたくてこの業界を目指したんですが、駆け出しの頃は、海外ドラマの吹き替えやドキュメンタリー番組のボイスオーバー(原音を残しながら、翻訳音声を重ねる手法)のお仕事が多かったんです。
やってみると、これがなかなか奥深くて難しくて面白くて。
その中でもとくに『ザ・ホワイトハウス』というシリーズは、転機になった作品だというような気がします。その現場で「あ、マイク前のお芝居ってこうやるんだ」ということを学んだ気がするんです。
例えば吹き替えの場合、原音として役者さんの声があってそこにアテレコをするわけですが、本来、まったく違う言語だから口の動きと声って合わないんですよ。なのに、ドラマを観るとまったく違和感がなく観られるわけじゃないですか。
で、先輩方の仕事を見ていると、何気なくお芝居をしているようで、ものすごく緻密な計算をされた上でセリフの掛け合いをしているわけです。ライブで。視聴者に違和感なく観てもらうために、言われなければ気づかないような細かな表現がちりばめられていて、簡単にできるようなことじゃないけど、見ているとすごく面白く感じられたんです。
駆け出しだった僕にはものすごい勉強になりましたし、職人的な仕事を裏方としてこなす背中がかっこよくて、「やっぱり声優の仕事、好きだな」と思えたんですよね。

――すごい世界ですね……! それを先輩方に教えてもらいつつ、当時の佐藤さんは収録にのぞんでいたと。
佐藤:いや、「誰かに何かを教えてもらえる」という世界ではないので、スタジオでの過ごし方含め、基本的には見て学ぶことがほとんどでした。
最初なんて「絶対に遅刻しちゃいけない!」と思うから現場に30分前に入るじゃないですか。そしたら誰もいなくて。「さて、どこで待とう」と思ってそこら辺にあるイスに座っていたら、後々になって「そこは主役の席だから」といって怒られたり(笑)。
それと驚いたのが収録中のマイク回し。例えばブース内に4本マイクがあったとして、それを30人の役者が入れ替わり立ち替わりで使っていくんですけど、誰がどのマイクを使うかは、割り振られていないんですよ。
――え、そうなんですか?!
佐藤:大体そのうち1本は、主役の方が使うマイクで、ほかの役者は残りの3本でやりくりするんですよ。「このシーンは、あの先輩がこのマイクを使っているような。だったら、自分はこっちのマイクかな?」とか、どこのマイクを使えばいいのか、逆算していく感じ。
しかも、「このタイミングで話すので、一瞬、このマイク使わせてもらっていいですか?」という感じで、ほかの役者さんと交渉したりしながら一瞬だけマイクを盗んでお芝居する、みたいな(笑)。
さっき「はじめまして」って挨拶したばっかりなのに、スタジオの中ではさもずっと同じ職場で働いてきたスタッフかのようなチームプレーが一瞬でできあがるんです。それもやり方を教わるわけではないので、やっぱり先輩のやり方を見て学んでいくしかないんですよね。
――収録中だけど、演技以外のことにも頭をフル回転させてるんですね。
佐藤:じつは、そうなんです。それだけのことやってるから当然、脳も疲れるし、当時は「そりゃあ先輩方、終わったら飲みに行くよなぁ」と思ってました(笑)。
ただ、コロナ禍以降は、わりと人数制限をしっかりした上で収録することが多くなったので、そういう技術がだんだんと継承されづらくなってしまっているんですよね。それはそれで今の時代に即した収録のあり方だな、とは思います。
でも、駆け出しの頃にそんな現場を経験をしてしまった僕にとっては、数十人で一つのドラマを作り上げる難しさと、それができたときの気持ちよさみたいなものが、声優の仕事の原体験として、懐かしさと一緒に刻み込まれているような気がします。
キャラと対話し、自分なりの解釈を提案する

――理論的に演技を組み立てていくタイプ、キャラが憑依するタイプなど、声優さんごとにもいろいろな役作りの方法があると思うんですが、ご自身はどんなタイプだと思いますか?
佐藤:僕もわりと、理論的に組み立てていくタイプですかね。「なぜこのタイミングで、この人はこんなことを言うんだろう」とか、「なぜこの人は、ここでこんな行動をとるんだろう」とか。物語上の役割とか。
もちろんマイク前に立ってお芝居をするときは、全部忘れてその人のつもりでセリフを発するんですけど、その心情の根っこの部分。そのキャラはどんなことを軸に生きているのか、どんな動機があって行動をしているのか。それを捉えて、そのキャラ自身に「まあそうね」と言ってもらえるように役作りしたいと思っています。
――じゃあ佐藤さんの中で、演じるキャラと対話していくような感じなんですね。
佐藤:そうなんです。ただ、僕の心の中で「合ってるよ」と言ってくれるキャラも、あくまで僕自身が作り出したものなので、仮に作り手側と僕で想定する表現が少し違ったとしても、「それもありだね!」って言ってもらえるような演技に落とし込みたい、という思いはあります。
多分それは、駆け出しの頃に吹き替えをやっていた経験があるからだと思います。
――というのは?
佐藤:映画やドラマの吹き替えの場合って、本来、演じている俳優さんが画面の中に実在するわけです。しかも、例えば世界的なアワードを受賞してしまうようなすごい俳優さんで、その声を「来週、アテレコお願いします!」と言われることもあります。
その俳優さんのつもりで演じたいとは思うけど、その人とイコールになることは難しい。でも、そもそも言語も人種も違うわけですから。でも作品としては、違和感なく観てもらえるように仕上げなければいけない。
そうすると、やっぱりどれだけその演じる人を咀嚼できたかが大事で、お芝居を通して僕なりの解釈を提案することで、「吹き替え版もありだね!」という着地点におさまることがすごく重要。駆け出しの頃に経験してきたから、今でもそうした考えが根幹にあるんだと思います。
『キャプテン翼』日向小次郎を
演じるときに考えていたこと

――2018年、そして2023年に放映された第4作『キャプテン翼』では、翼のライバルである日向小次郎を演じられました。歴代、先輩声優が演じてきた名キャラを務めるにあたって、どんな気持ちで演じられていたんですか?
佐藤:最近アニメでも、往年の名作のリメイクってたくさんあるじゃないですか。『キャプテン翼』でももちろんそうですが、ほかの作品で役を引き継がせていいただくときにも「オリジナルはオンリーワンだな」という気持ちはやっぱりどこかあるんですよ。
それってもう小鳥の刷り込みとか、初めて好きになった人みたいな感覚で。
今回の場合、僕にとっては、初代の鈴置洋孝さんが演じられた日向小次郎が正にそんな感じですが、同じくアニメで日向を演じられた檜山修之さんや子安武人さんと歴代の日向それぞれが、誰かにとってのオリジナルだと思うんです。その初めての“好き”って、上書きできないと思うんですよ。
だから日向を演じる上ではそれを踏まえて僕なりの日向を表現するつもりでアプローチしています。
――先輩方が演じてきた日向小次郎を、どんなふうに咀嚼していくんでしょうか。

©高橋陽一/集英社・キャプテン翼シーズン2 ジュニアユース編製作委員会
佐藤:役への向き合い方というものは演者によって違うと思います。どんな“日向らしさ”をピックアップしているのかの違いだと思うんですよ。荒々しさなのか、上昇志向なのか、それとも家族思いなところなのか。
ただ、一番大事なのはやっぱり日向の根っこの部分。彼が、何を軸に生きているのかということ。それを掴まえられれば、たとえ歴代の先輩たちと声音や表現の仕方が違ったとしても、僕が演じる日向小次郎を受け止めてもらえるんじゃないかと思うんです。
――「先輩声優たちがいる」ということよりも前に、「日向小次郎という人物がいる」ということですね。それを捉えた上で、佐藤さんなりの日向を演じていくと。
佐藤:そういうイメージです。ただ最終的には「僕の演じる日向がどうのこうの」ということでもなく、『キャプテン翼』という作品自体を楽しんでもらえることが、声優としては一番幸せかなと思います。
ドラマCDの収録は、よりイマジネーションが大事

BL作品のドラマCDなどにも多数ご出演されていて、そのセクシーボイスに心を掴まれた女性も多いと思います。ドラマCDの収録ならではの心持ちとかはあるんでしょうか。
佐藤:そうですね……ドラマCDの収録なんかだと、原作者の先生もその場に同席して聴いていただく機会も多いんですが、その先生がものすごく楽しそうに僕らのお芝居を聴いてくださることが、僕たちにとっては嬉しいし、救いだなって思います。
原作者の先生って、言ってみればその世界の創造主なわけですよね。僕らの演じるキャラクターも、セリフも、そのすべてを作り出した人がその場にいるので、もちろん緊張感もあるのですが、聴いていただくからには「楽しんで、喜んでもらいたい」という気持ちは一段と強くなりますね。
何より、収録を聴いていただくということは、「一人目の視聴者」ということにもなるので、やっぱり「先生に喜んでもらえなければ、視聴者のみなさんにも喜んでもらえないだろう」という気持ちで、いい作品にするために力を尽くしたいという気持ちも強くなります。
――ドラマCDの場合、いわゆる“画”がないまま収録するじゃないですか。結構、事前にしっかり打ち合わせをしたりするんですか?
佐藤:それが、そうでもないんですよ。大体のドラマCDって60分ものだとしても一発録りなので、最初に数ページ分、キャラクター確認のためにテストしたら、あとはもう回しっぱなし。だから事前に演者間でこうしようああしようという打ち合わせはしません。
といっても台本にはセリフしか書いていないので、収録中は、相手の演技を聴きつつ頭の中で場面をイメージしながら、シーンを組み立てていくような感じです。

――すごい、イマジネーションがとても大事になってくるんですね。
佐藤:僕個人の思いなんですけど、原作があるものなので、例えばマンガをめくりながらそのCDを流したときに、破綻がないようにしたいんですよね。
音声作品だから、もちろんそれ単体としても臨場感とか、奥行きみたいなものは感じてもらえるけど、マンガと一緒に楽しんだときでも、「なるほど」って思ってもらえればいいなと。
でも、逆に事前にそこまで打ち合わせをしていないからこそ、その目指したいもののイメージが相手の声優さんとぴったり噛み合ったときは、阿吽の呼吸みたいな感じで収録がすごく楽しくなります。
――それは、原作が好きでCDを聴いてる人からしたらめちゃくちゃ嬉しいですよね。
佐藤:結局、そこなんですよね。
僕たちがいろいろな工夫をしたり、場面をイメージしながら演技をするのも、あくまでその作品を聴いてくれた方にどれだけ楽しんでもらえるかが一番大事で。本当、それに尽きると思います。
燭台切光忠と江雪左文字の
二振を演じる『刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-』の魅力
――今年の春にアニメ『刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-』も放送しました。原案ゲームとアニメでは燭台切光忠と江雪左文字の二振りを、佐藤さんが演じています。改めてこの作品の魅力を教えていただけますか?
佐藤:ゲームから始まり、様々なメディアで展開しているシリーズなんですが、描かれるメディアによって、別個体だと僕は認識しているんですよね。それが『刀剣乱舞』の面白さでもあるのかなって。
そもそも原案ゲーム内では、プレイヤーごとに解釈が分かれる作品だと思ってます。だからアニメならアニメ、舞台なら舞台というふうに、それぞれに立ち上がる世界での燭台切光忠と江雪左文字の姿があって、いい意味での“違和感とブレ”みたいなものを感じるし、作品ごとに感じ取れるのが、僕に取ってはすごく面白いなと思っています。
メディアごとに表現の仕方が全然違うけど、それでも燭台切光忠は燭台切光忠だし、江雪左文字は江雪左文字だとわかる。ほかのアニメ作品やシリーズではなかなか味わうことができない、不思議な魅力をもった作品だと思います。
取材・文/郡司 しう 撮影/小川 伸晃