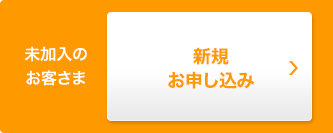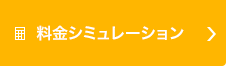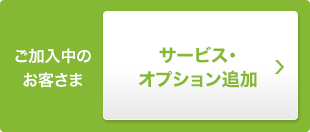ここは長い歴史を誇る京都太秦の松竹撮影所。時代劇の熟練スタッフが技と結束力を駆使した
「雨の首ふり坂」の現場のウラ側を、時代劇研究家ペリー荻野が、現場からリポートします!

ペリー荻野
愛知県出身のコラムニスト兼時代劇研究家。
時代劇専門チャンネル公式Webサイトで「ペリーのちょんまげ」執筆中。
雨粒づくりはアナログだった!
「雨降らし」の現場に潜入
撮影所に到着するとすぐに梅雀さん演じる源七が、決意を秘めて雨の中を歩き出すシーンに立ち会えました!「晴れているのに、どうやって撮影するの?」と思って見ていると、用意されたのは直径7㎝ほどの散水ホース。水が高く飛び「もうちょい飛ばさな!」「もっと右や!」と掛け声が続きます。なんでも、自然に降る雨粒は、カメラでは撮れないから、ホースで霧雨から豪雨まで作るんですって。太陽が雲に隠れるのを待って、やっと撮影。源七の哀しい背中が雨の中に浮かんで…。雨粒を作るのに、涙ぐましい努力があるんですね〜!

雨の強さや粒の大きさはホースの押さえ加減で調整。こんなところにもプロの技が!


スタッフの呼吸がひとつになって、「雨の名シーン」が生まれました!

黒を基調とした源七の合羽(右)は長くて重っ!
一方、旅を続ける半蔵の合羽(左)は“ボロボロ”感が絶妙!

「秘技・汚しの術」とはいかに?
衣裳部の職人魂を見た!
次に各役者の衣裳がずらりと並ぶ、衣裳部にお邪魔しました!担当の真柴さんはとってもチャーミングな女性。「いつも監督さんや役者さんの思いを伺って衣裳合わせをします。今回ならば、監督や梅雀さんとも『源七は黒』と意見が一致したので、黒の着物を3枚新調しました。大杉さんのは、『汚れたボロが着たい』とのご要望で、一番手間がかかりましたね(笑)」ボロが一番手間?「はい。長年着込んでいるような感じを出すため、ヤスリをかけ、手でもんで〝汚し”やボロボロの感じを出したりしています。縫い目をつったり、わざわざ染めて仕立てて〝汚し”を出したりもします」細かいテクニックに、職人芸を見ました!


黒を基調とした源七の合羽(右)は長くて重っ!
一方、旅を続ける半蔵の合羽(左)は“ボロボロ”感が絶妙!

細かいところにもこだわりが!
小さくても縁の下の力持ち「小道具」
続いて、小道具・浅居さんに直撃!「役者によって刀の特徴も変えています。源七や万次郎は大刀より短く、短刀より長い渡世人の長脇差を、万次郎の刀には少し金属の装飾でギラギラした若さを出しました」物語のカギとなる巾着袋にも凝り、5回も作り直して完成したのは撮影当日の朝!「監督ともう少し色をにじませようとか相談して、いろいろ変えました。自分がイメージした道具と、照明、カメラ、監督の意向などが、全体にまとまっていくのが一番気持ちいいですね」熱意には頭が下がります!

表紙撮影にはギラギラ感を出すため鉄製(左)を、シーン撮影には俊敏さを出すため軽いアルミ製(右)を使うなど、刀の材質も変えているんですって!

これがドラマのカギとなる巾着。注目あれ!

小道具:浅居丈葉さん

彦太郎が饂飩を打つシーンも、本物の饂飩屋さんに教えてもらったそうです!
本当に調理できちゃうんです
リアルな饂飩屋さんに感激!
源七と彦太郎の運命を変える饂飩屋さんのセットは、監督いわく〝幸せの象徴”の場。食器も食材もすべて本物なのはもちろん、セットの中で、いつでも本当に饂飩が打てるんですって!炭火でお湯を沸かし、火を調節しながら、湯気やかまどに〝演技”させることで、お店の繁盛ぶりを表現するのもプロの技。饂飩の湯気も、ほっとする人の顔も本物なんですね〜!

彦太郎が饂飩を打つシーンも、本物の饂飩屋さんに教えてもらったそうです!
“チャンバラ”の世界は奥が深い
凄みのある殺陣に息を呑む
時代劇と言えば、なくてはならないチャンバラシーン。今回の殺陣を指導したのは、ベテラン殺陣師の菅原さん。「若者が感情的に戦う殺陣も、梅雀さん、大杉さんらの年を重ね、円熟味を感じさせる殺陣もどちらも素晴らしい。彼らの結末には僕自身もじーんときました」源七が川で追っ手に挟まれるシーンで、「梅雀さんには、水の中に敵を誘い込む難しい殺陣を要求しましたが、重い合羽をタイミングよく脱いで、速い動きにもしっかりと応えてくれました。貴大さんも、役柄の感情がこもった殺陣をしてくれて、見事でした」

川の中で立ち回る、まさに「殺す」ための殺陣

殺陣:菅原俊夫さん
障子の切り貼りから、町並みまで
時代劇の世界を作りだす美術

美術:原田哲男さん
最後におじゃましたのは、作品の舞台を作り上げる美術さん。担当の原田さんから見せていただいた、精密なスケッチの数々にびっくり!実際のセットを見ると、スケッチと全く同じに作られているのにさらにびっくり!カメラや出演者の導線を考え、可動式の家も活用しオープンセットの町並みを変える大きな作業から、障子や灯りの切り貼りなどの細かい演出まで、すべて美術さんのお仕事なんですって。「いろいろ味付けし出したらキリがないですが(笑)、細かいところを見てもらえるとうれしいです」(原田さん)まさに物語の世界観を作り上げるキーマンですね!

スケッチだけでも十分に趣がありますが…


実際のセットもスケッチそのまま!

物語の舞台となる饂飩屋の台所も…


格子から差し込む陽光を見事に再現!

灯りの切り貼りも温かみを感じます

看板もスケッチに忠実です!

こんなところに“すずめ”が!
感動のクランクアップ!
いよいよラストカットに立ち合いです。撮影所に響きわたる監督の「OK!」コール。
皆さん、作品への思い入れもひとしお。早く作品が見たくなりました。
これから時代劇を見る目が変わりそうです!
魅力再発見!
「見たい」をカタチにするオリジナル時代劇
企画・プロデュース 宮川朋之
地上波民放から時代劇が激減し、時代劇ファンは悲しんでいます。地上波は無理でもJ:COMなら時代劇が楽しめる。そんな夢をカタチにしたのがオリジナル時代劇です。最初は不安でした。お客さまは新しい時代劇を求めているのだろうか。はじめてオリジナル時代劇を放送した日、そんな心配は杞憂に終わりました。視聴者からの賛美、激賞を忘れることはできません。
だから今も創りつづけます。お客さまの「見たい」のために。