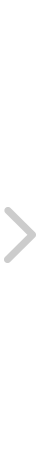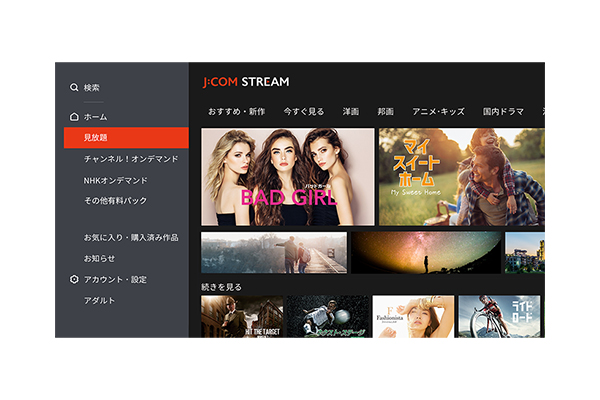悪あがきしてでも立ち続ける

――新人声優やこれから声優業界をめざす方に向けて、速水さんからメッセージをいただけますか?
速水:これは声優としての基本の基本ですが、言葉、日本語に対する感覚を研ぎ澄ますということ。
たとえば、単位につく半濁音。「1分(ぷん)」、「2分(ふん)」、「3分(ぷん)」……「4分」は?
――“ふん”?
速水:そうですよね。いま、若い方は「4“ふん”」って言うんですよ。でも僕らの時代は「4“ぷん”」だった。この違いはすごく曖昧で、僕は日々「どっちになるんだろう」「NHKはどっちで言うんだろう」と考えながら過ごしていたりします。
ただ、これは「どちらが正しい」というものではなくて、変化の流れにあるときにどこかでスタンダードが定まるものだと思うんです。
こうした音便や言葉のアクセントに対して敏感でないと、プロとして対応できない場面が出てしまう。
僕たちに大事なのは演技年齢であって、実年齢ではない。20代の男性を演じるはずなのに「4分(ぷん)」と言ってしまうと、視聴者にとってはノイズになってしまいますから。
――……ライターとして耳が痛いです。
速水:もう一つ思うのは、時代や場所による喋り方の違いですよね。たとえば、ヨーロッパの薔薇戦争の時代の王族を演じるとして、どんな喋り方で、語尾はどうなるのか。現実的には、言語も時代も違うところに日本語で声をあてるので、ありえないことです。でも、作品としては「ありえる」と思えるレベルにまで持っていかなければいけない。
どれだけ多くの作品を観て、受け取ったものを蓄積しているか、演技に説得力をもたせるためにはすごく大切なんです。いまの新人や若い声優を見ていると、まだまだそこまでできている声優は多くない。
日本語という言語自体が時代によって変わるなかで、僕らはキャラクターの年齢、作品の時代背景を考えながら演じなければいけません。「言語学者になれ」とまでは思いませんが、そこに対する感覚は養っておいたほうがいいと思います。

――速水さんは、今後どんな声優でありたいですか?
速水:あがき続ける。あがいていることが、商品であり続けられる声優でありたいですね。年齢にも、肉体にも、自分が持っているちっぽけな感性にもあらがい続けたい。
これから先 演じる役って、いまからは想像できないようなものがたくさんあると思うんですよ。そのつど、僕はあがかなければいけないし、商品にしなければいけない。たとえ悪あがきだとしても、その意識は持ちたいですね。
――あがき続けるためには、どんなことが必要ですか?
速水:肉体を鍛えること、あとは心を柔らかく保つことですかね。自分の内側からちゃんとエネルギーが出てくるように。
ステージ上であっても、マイク前であっても「そこに立っていられる」って実はすごいことなんですよ。見ると簡単なように思えるかもしれませんが、人によってはそこに「立てない」と感じてしまうほど。最初の頃は、僕だってちゃんと立てていませんでしたから。
緊張感、責任感、プレッシャー、重圧、期待。いろいろなもので押しつぶされそうになるなかで、そこに速水奨として立っているためには、自分の内から湧き出るエネルギーみたいなものがないと絶対に立てない。
悪あがきしてでもエネルギーを発し続けて、ステージやマイク前に立ち続けたいですね。
『BLEACH千年血戦篇-相剋譚-』が放映
藍染惣右介を演じてきて
――2024年秋クールでは、『BLEACH 千年血戦篇』第3クールとなる『BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-』が放映されます。『BLEACH』にまつわる思い出といえば?
速水:やっぱり藍染と一護の対決シーンですかね。それを収録した日は、朝 収録前に家で台本を読んでから、気持ちを作ってスタジオに行ったんですけど、小さなスタジオに40人くらいの声優が集まって。だけどその回はほとんど、僕と一護のバトルなんです。
それを40人の声優が囲んで見ているなか、芝居して。もう、ちょっとしたライブですよね。そんな環境だから緊迫感もあったし、ギャラリーがいて気持ちがのる部分もあった。言ってみればボクシングのリングに立っているような、ちょっとしたトランス状態。自分がどんなことを詠唱したのかも憶えてないくらいですから(笑)
あの収録は忘れられないですね。
――現場の緊迫感が伝わってくるようです。藍染惣右介のキャラクターとしての魅力もお聞きできますか?
速水:一護との戦いは、ある意味で一護を覚醒させるための戦いだったんじゃないかと思える部分もあるし、僕の中では、藍染を正義か悪かという観念で語るのもどこか違う気がしているんですよ。
優しさというと違うけれども、究極まで行ったところに、かすかに愛が見える感じがするんですよね。これは演じたからこそわかることなのかもしれない。だけど、僕はそれを魅力に感じているかな。
――その“かすかに見える愛”は演じるときにも意識されていたんですか?
速水:いや、それはまったく(笑)。演じているときにフォーカスしていたのは、藍染の最強の絶対悪としての面だけでした。ただ後になって思い返したときに、そうなんじゃないかという思いが湧いてくるんですよね。
『BLEACH』のゲームで藍染のセリフを録り直したとき、自分のかつての演技を思い返して「すごいことをやっていたんだな、僕」という気持ちになりました(笑)。

©久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ
――最後に『BLEACH』という作品の魅力をお聞きできますか?
速水:初めて藍染惣右介を演じたときには、こんなに広がっていく作品だとは思ってもいませんでした。それは多くの人に愛されるという意味でも、展開する物語という意味でも。
前々回、『グレンダイザーU』のお話をしたときにアブダビに行った話をしましたが、向こうにも『BLEACH』ファンはすごく多いんです。ある王族の方は刀を6本も持っていらして、「刀身にサインしてくれ」と(笑)。世界に広がっている作品なんだなぁというのを肌で感じましたね。
物語という意味では、戦いが果てしなく続き、強大な敵が次々に現れて、その中で“強さ”とはなんなのかをひたすらに考えてしまう。一護をはじめとする登場人物の成長は、「どこまで行けるんだろう」という果てしない広がりを感じさせてくれるし、限界突破的な楽しみ方がすごくありますよね。これほど少年心をくすぐる作品はそうない。
『BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-』も話がクライマックスに差し掛かっていくなかで、『BLEACH』らしさがいかんなく発揮されていると思うのでぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。
取材・文/郡司 しう 撮影/小川 伸晃