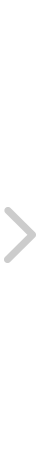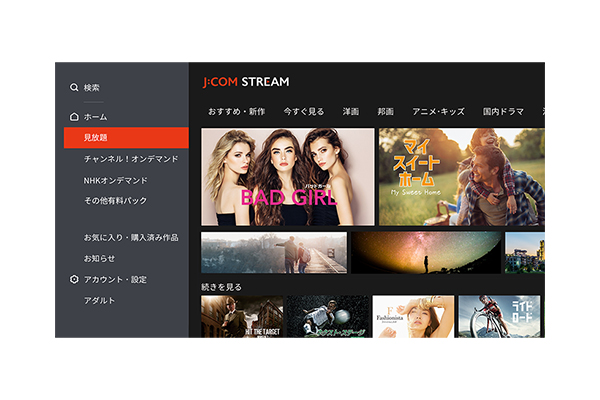声優・梶裕貴
ロングインタビュー #2
どん底だった下積み時代。声優として現場に
行けるようになることが何より嬉しかった
2024年11月22日更新
KAZIINT
ERVIEW
『進撃の巨人』のエレン・イェーガーをはじめ、『七つの大罪』のメリオダス、『僕のヒーローアカデミア』の轟焦凍、『鬼滅の刃』の錆兎など、数々のヒット作で主役や人気キャラを演じる梶裕貴さん。その透明感ある声と繊細さながらも力強い演技は、キャラの魅力を深く引き出し、その存在に命を吹き込みます。その圧倒的なパフォーマンス力をもつ梶さんが大事にしているのが、挑戦心を持ち続けること。未来を見据え、つねに新しいことに挑戦し続ける自身のことを「つねにファイティングポーズを取っている」と語ります。このインタビューでは全3回にわたり、梶裕貴さんの出演作品に対する思いや、声優としての歩みをひもときながら、その人となりに迫ります。
夢多き少年の道を拓いた大先輩の言葉

――今回のインタビューでは、幼少期の頃からお話をお聞きしていきたいと思います。まず、小さな頃はどんな性格のお子さんでしたか?
梶:基本的には、明るく元気な子どもの部類に入るのかなとは思います。
ただ、人見知り、恥ずかしがり屋な面もあるので、家族や友達の前ではひょうきんな振る舞いを見せつつも、知らない人が多い場所に行くとひっそり静かにしている、みたいな両極端な一面もありました(笑)。
小・中学校では、学級委員長や生徒会長を務める機会が多かったですかね。とはいえ元々、人前に立つのがそんなに得意なタイプではなかったので、先生や家族、友達から期待してもらうことで、「自分はリーダーを頑張るべきなのかな?」と信じこんでいた部分があったように思います(笑)。「それなら頑張ってみようかな」と。
いま考えてみると、自分が本当にやりたかったわけでもない気がするし、向いているとも思わないので、当時は自分で自分をそういうキャラ設定にして、どこか演じていたのかもしれませんね。
――小さい頃はどんなキャラクターが好きだったんでしょうか?
梶:幼稚園の頃は特撮系の戦隊ヒーローものが大好きで、やっぱり中心のレッドに憧れていましたね。遊ぶときは、とうぜん友達とレッドの取り合い(笑)。それでも、みんなでレンジャーごっこをするのが本当に好きでした。
当時の写真や動画を見返すと、お面や変身ベルト、武器などを持ってレッドになりきっているものばかり。とくに憧れていたのが、「敵の攻撃でダメージを負い倒れつつも、もう一度立ち上がって悪に宣戦布告するシーン」で、よく母にそれを撮影してほしいと頼んでいたみたいです(笑)。
――ピンチになってからのヒーロー像が好きだったんですね。
梶:「窮地に陥ってからの反撃の狼煙」というところに、かっこよさの美学を感じていたんでしょうね。でも、その美学は今にもつながっているような気がしていて、不思議と、僕の演じる役のほとんどがそういった見せ場を持っているんですよね(笑)。
小学校の頃に『るろうに剣心』『名探偵コナン』といった、いまでも続く人気シリーズが始まり、それはもう大好きでした。中学生だと『ONE PIECE』『NARUTO』などでしょうか。
――小さい頃に思い描いていた将来の夢はあったんでしょうか?
梶:子どもの頃はとにかく夢がいっぱいありましたね。
サッカー選手、漫画家、ゲームデザイナー、科学者、オリンピック金メダリストなどなど。もっと言うと、それこそ『名探偵コナン』や『るろうに剣心』に影響されて、探偵や侍になりたいと本気で思っていた時期もありました(笑)。
とにかくハマるものがあると「トップとして、その道を極めている自分」を思い浮かべるんです。そのときどきで将来の夢は変わっていましたが、そのつど本気でしたし、常に全力で気持ちを注ぎ込んでいたと思います。
――そこから声優への興味というのは、どうして生まれたんでしょうか?
梶:中学生の頃、どなたのお言葉だったのかを覚えていないんですが、声優の大先輩が「声優という職業は、何を頑張っても全部自分の力になる仕事」という言葉を仰っていたのを見かけたんです。
そこで、「ということは、声優なら、やりたいことを一つに絞らなくてもいいんだ」という発想が生まれて。いろいろなことに興味があってなんでも頑張りたい自分にとって、もしも声優の定義がそうであるならば、いままで通り、自分の好奇心のまま、真っ直ぐな熱意のまま頑張っていれば、声優という職業に生かせるのかもしれない。
そう考えが結びついたときから、「声優になりたい」という気持ちが固まって、自分の思い描く夢の向かう先が、一つに集約されていく感じがありましたね。
いま、実際に声優になってみて、それはまさに感じているところ。演じる役次第で、科学者にも、アスリートにも、探偵にも侍にもなれる。キャラクターを通じていろいろな人生を体験できるのは、まさに自分の夢が叶っていく感動があります。
勝負すらできなかった3年間

――ここからは、下積み時代についてもお話をお聞きしたいと思います。梶さんは、いわゆる下積み時代があんまりなかったような気がするんですが……
梶:何を根拠に!(笑)。まあ時間的な長さの話でいうと、周りから見ると短いと思われる方もいらっしゃるのかもしれませんが…僕にとっては、やはりすごく長く苦しい下積み時代でした。
高校在学中から、週末に養成所のレッスンには通っていたものの、高校卒業と同時に家を出て一人暮らしを始めて……そこからレッスン以外はバイト漬けの毎日。もうバイトのために生きてしまっているような状態で、とてもしんどかったです。
大きな夢として、「売れたい」「主役をやりたい」という気持ちはもちろんありました。けれど、それ以前に「どんな形でもいいら、とにかく現場に行って仕事をしたい」という思いが強かった。とはいえ、なかなかそんなチャンスには恵まれませんでしたね。
――オーディションも受けられていたんでしょうか?
梶:所属声優も多い事務所でしたし、先輩声優の活躍がまぶしいばかりで、自分は「事務所内でのオーディションを受ける候補」にすら入れていない状態でした。簡潔に言えば、「チャンスをつかむためのチャンスすらない」というような状況。
18歳で家を出て、自分としては1秒だって無駄にしたくないけれど、自分だけの力ではどうにもできなかったわけです。同期が次々と現場に呼ばれていく様子を横目で見ながら、焦燥感と羨ましさで、どんどん自己嫌悪が強くなっていきました。
高校卒業後、貴重な十代の時間をふくむ数年間。気持ちはあるのに、実際には何もできていない閉塞感に苛立ちながらも、なんとか歯を食いしばってバイトで生活費を稼いでいました。
――気持ち的に、腐ったりはしなかったんですか?
梶:いや、腐りかけていましたよ。それでも、やめようとまでは思わなかった。というか、そもそもまだ何も始められていないわけで、「やめると?」という感覚でしたね(笑)。
バッターボックスに立った上でアウトになったのなら、自分の力不足に納得もできたかもしれないですけど、まだベンチにも入れていなかったですからね。まずは「勝負させてくれ!」とずっと思っていました。
――それがどんなきっかけで変わっていくんでしょうか。
梶:やさぐれた気持ちを抱えながらもなんとか続けているうちに、少しずつオーディションにお声がけいただけるようになって……だけど、そう簡単に受かるはずもなく。
そんな日々を繰り返しているうちに、アニメの主演オーディションに参加させていただく機会をいただいて。最初はテープ審査と書類選考、次にスタジオ。通常、二次選考までで結果が出るオーディションが多いのですが、そのタイトルは三次選考まであるような、かなり力を入れた作品でした。
ありがたいことに最終選考まで残ることができ、いざ最後のスタジオ審査に行ってみると、その役で残っているのは、僕とあと一人だけというのがすぐにわかって。
その瞬間、「どちらか一人が受かって、どちらか一人の人生が変わるんだな」という当たり前の現実を、直感で理解した感覚がありましたね。