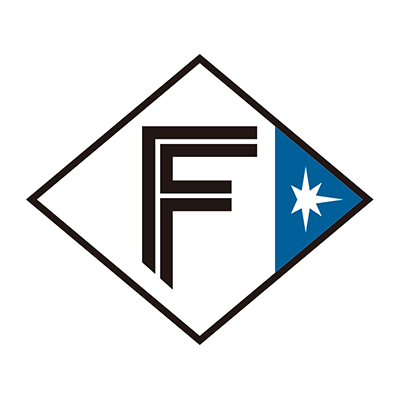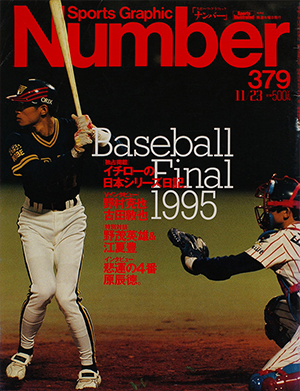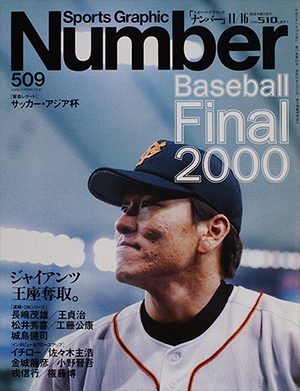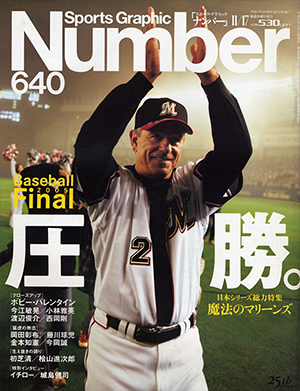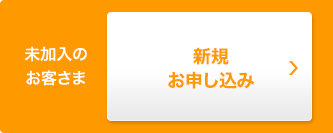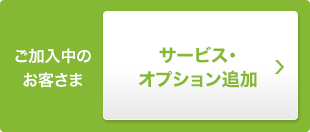創刊40周年を迎えるスポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』のバックナンバーから、
球団ごとの名試合、名シーンを書き綴った記事を復刻。2020年シーズンはどんな名勝負がみられるのか。

2017年松坂大輔
[証言ノンフィクション]
デビュー戦「155km」の衝撃。
text by Tadahira Suzuki
photographs by Hideki Sugiyama
「あんな空振りしたことない」
18歳の新人が投じたストレートが
プ口屈指の強打者を粉砕した。
当事者が語る“怪物”誕生の真実。
4月7日、本拠地・東京ドームのグラウンドに足を踏み入れた日本ハムの主砲・片岡篤史は、肌にいつもはない熱気を感じていた。屋内とはいえ春先はまだ寒いはずだが、この日はスタンドを埋めた人たちの熱がグラウンドまで伝わってきた。
片岡が初めて松坂大輔を見たのは前年夏の甲子園だった。
「春夏連覇は俺たち以来だったから」
片岡はその11年前、PL学園の主砲として春夏連覇を成し遂げた。それ以来の王者が誕生し、その中心に怪物と呼ばれる投手がいる。だから、シーズン中ながらテレビに視線を送ったのだった。ただ、対戦前の松坂への意識はあくまで1人の新人に対するものでしかなかった
「変化球投手やろ。まだ高校生やんけ。試合前はそんな感じで考えていた」
開幕からの3試合で片岡は打率5割と、好調ビッグバン打線の王様として君臨していたのだから、それも当然だった。
初回、井出竜也と小笠原道大が打ち取られると、3番片岡はゆっくりと打席に入り、松坂と向かい合った。2球目。150kmがきた。明らかに前の2人とはギアを変えていた。新人らしからぬ度胸にグリップを握る手に力が入る。そして4球目。片岡は最初の衝撃に出会う。膝下へ曲がり落ちるスライダーを微動だにせず見逃した。少なくとも見ている者はそう思った。だが、無表情の裏で片岡の鼓動は速くなっていた。
「あんなキレは見たことない。正直、手が出なかった。曲がってからも強いスライダー。あの1球で相手が高校生だという考えを頭の中から消した」
カウント2-2。西武の捕手はベテラン中嶋聡だった。片岡は次の勝負球、ストレートでくると直感した。確信に近かった。
「あの時代のパ・リーグはお互いわかっていても力勝負。そういう空気があった」
グリップを握る力は、さらに強くなった。18mの先で放たれたボールが一瞬にして目の前で巨大化する。それをフルスイングで迎え撃つ。次の瞬間、白球はバットのはるか上を通り過ぎていた。かつてない加速度で回転した体はバランスを失い、片岡は地面に倒れた。両手が遠心力に耐え切れず、バットが放り出された。仁王立ちのルーキーとひざまずく主砲。スコアボードにはその空振りの壮絶さを裏付けるような数字が表示されていた。
155km――。
東京ドームはどよめきに包まれた。
東尾修は後に語り継がれるこの1球を西武ベンチで見ていた。胸に抱いていた不安がスーッと消えていくのを感じた。
「あれは今でも大輔がプロで放った一番のボールだったと思う。あれを見て『ああ、大丈夫だ』とホッとしたね」
松坂のデビュー戦をこの試合に決めたのは当時、指揮官として5年目の東尾だった。甲子園の怪物として1位で獲得した大物ルーキーは開場したばかりの西武ドームの目玉だ。当時の堤義明オーナーも、中継テレビ局の幹部も、開幕カードでの本拠地デビューを望んだ。だが、東尾は譲らなかった。
「大輔は足首が硬かったから傾斜のある東京ドームのマウンドの方がいいというのもあったし、何よりも勝ちをつけていいスタートを切ることが最優先だった」
松坂との物語が始まったのは前年秋のドラフト会議、東尾の右手が交渉権を引き当ててからだった。その時、松坂は横浜ベイスターズ以外の球団が交渉権を獲得した場合は社会人に進むと公言していた。だからドラフトから数日後、都内の焼肉店で極秘に本人と両親との会談をセットした。
説得のために東尾が選んだのは“ストレート”だった。特別扱いはしない。客寄せパンダにもしない。日本シリーズ第1戦に先発する投手に育てる。真っすぐに訴え、最後に、あるものを取り出した。自身の200勝ボールだった。自宅を出る前、娘の部屋にあったものを思わず手に取ったのだ。
「このボールの重みを感じて欲しい。君が200勝したら返してくれ」
東尾はそう言って手渡した。まだライオンズが西鉄だった時代から15年、じつに586試合をかけて手にしたそのボールの重みを18歳に感じろというのだ。
「高校3年生の大輔は想像以上のところを目指していた。俺らの頃はそんなものわからなかったけど、大輔にはそれがわかる」
2年前の8月18日、
松坂から電話がかかってきた。