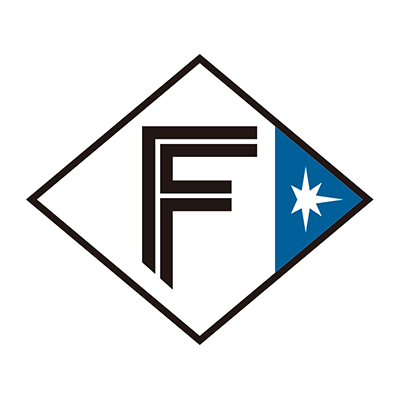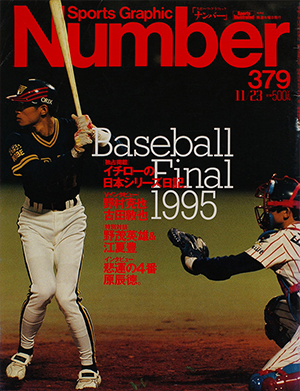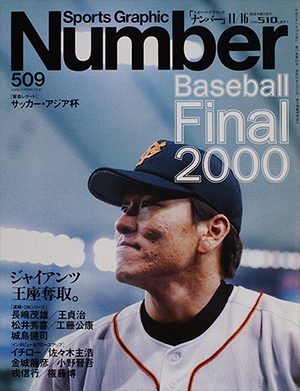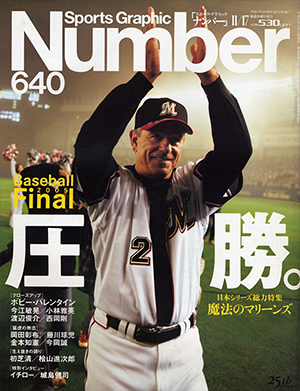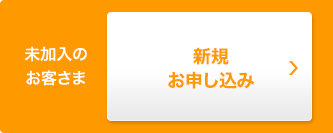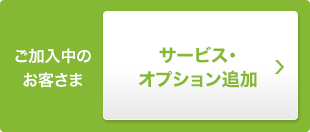創刊40周年を迎えるスポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』のバックナンバーから、
球団ごとの名試合、名シーンを書き綴った記事を復刻。2020年シーズンはどんな名勝負がみられるのか。

1985年阪神 日本一
いまここに甦り!猛虎魂。
文 村山 実
その、歓喜の一瞬……わがタイガースの戦士たちが、こぼれるように笑顔をふりまくのを見ながら、なぜか私には、一人の男の顔がフッと浮んだ。
江夏豊である。
――あの時、あの顔以来の〝タイガース魂〟をみなぎらせた男たちの顔に、私の血はたぎった。こいつらは、見事に命脈つきようとしていた〝猛虎魂〟を甦らせてくれたのだ!
あれは昭和45年10月12日の甲子園、対巨人戦だった。タイガースは巨人を半ゲーム差に追いつめていた。試合は3-1とリードして迎えた7回、マウンド上の江夏は一死満塁の大ピンチに立った。
打席には王がいた。そのとき私は兼任監督。前日に3-0と巨人を完封していたのだが、頼りのエースが苦境に落ちた以上、リリーフの準備をした。
江夏はたちまちにして王をカウント2-0に追い込み、3球目を外角低めにズバッと快速球。王が手も足も出ないほどの球であったが、主審谷村の判定は非情にも「ボール!」。みるみる江夏の顔がまっ赤になっていく。誇りと自信が傷つけられた時、投手はマウンド上で、〝ガラスの心臓〟に変化してしまうものだが、私には江夏の怒りが手にとるようにわかった。
江夏は、同じところに、同じストレートを意地になって続けた。いずれも判定は「ボール……」。王は結局、四球となり、押し出しの1点。続いて打者は長島。江夏はその長島に対しても、徹底してストレートを配していった。長島のバットが金属音を残し、打球は左翼へのライナー。逆転決勝タイムリーとなってとんだ。
唇をかむ。目は血走っている。そのまま江夏はマウンド上に両ヒザをつき、崩れて、すわりこむ。
この瞬間に、あのシーズン、あと一歩まで巨人を追いつめたタイガースのVは、音をたてて崩壊していった……。
だがしかし、私は妙に“悲しさ“はなかったのだった。それは、江夏豊が、シーズンのチームの運命がかかった場面で、天下のONを打席に迎えて、一球たりとも逃げることをしなかったことにある。江夏ほどの男だ、ピンチを断つテクニックはある。ごまかしもきくのだ。しかし、彼は、自らのウイニング・ショットを「ボール」といわれた怒りから、あえてもう一度挑戦していった。
それは、勝ちさえすればよい……という精神なら、むしろこっけいなことかもしれない。だが、私は思う。伝統のあるタイガースの一員としての誇りがあるのなら、そこで逃げてはならないのだった。だから、江夏は、グイグイと速球一本やりでON砲に対し、結果は玉砕していった。
人はこれを「負けちゃあしょうがない」というかもLれないが、実は、これこそ、〝タイガース魂〟そのものなのであった。いつ、いかなるときでも、誇りを失わず、戦いを挑む……。それはときとして、惨めな結果に終わるかもしれないが、そんなことをおそれているような男は、タイガースの本当の戦士とはいえない。
崩れる江夏に、私はヤケドをしそうな〝炎〟を見た。
その〝炎〟が甦ったのだ。
掛布がいた。岡田がいた。真弓、池田、中西、バース。まさに炎の男たちの描いてくれた21年ぶりの饗宴に、私も酔った……。
私は37、39年と、幸せなことに2度優勝の一瞬に参加できた。当時、私と吉田監督は、投、打の柱として競い、共に闘った。私がピンチに立つと、吉田さんはすぐマウンドに駆け寄り「ムラ、空を見ろ、空を……」と、ひと呼吸おくことをすすめてくれたし、再三のファインプレーで救ってくれた。逆に私は、吉田さんのたたきだした貴重な1点を必死で守った。
世評ではライバルとして見るが、こと、勝つことに関しては、われわれは、〝炎の軍団〟と化し、そんな低次元のことは考えもしなかったのである。
われわれは、あの37、39年のときも、常にチャレンジャー精神を忘れなかった。以後、21年間、なんと長き、〝空白〟があったことか。しかし、私の監督時代(45~47年)も、吉田さんの最初の監督時代(50~52年)も、いや、多くの指揮官が、けっして、はじめから諦めて戦っていたわけではない。誰もがタイガースの伝統という十字架を背負い、血を吐く思いでチャレンジしていったのだった。