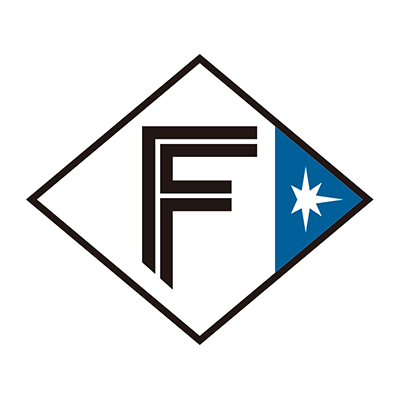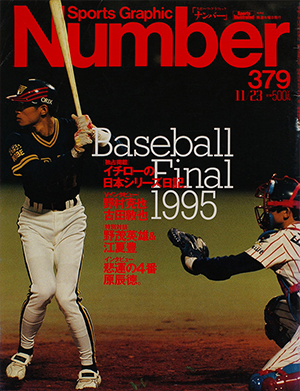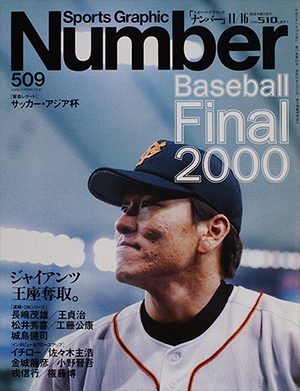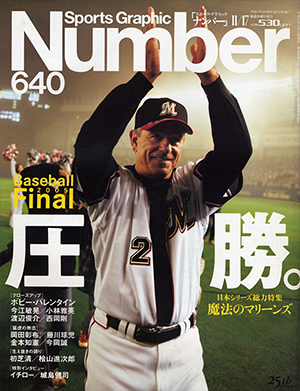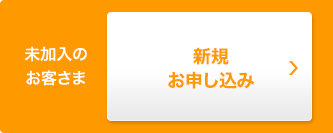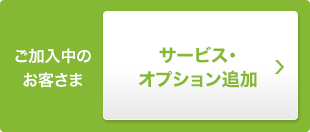創刊40周年を迎えるスポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』のバックナンバーから、
球団ごとの名試合、名シーンを書き綴った記事を復刻。2020年シーズンはどんな名勝負がみられるのか。

2017年松坂大輔
[証言ノンフィクション]
デビュー戦「155km」の衝撃。
text by Tadahira Suzuki
photographs by Hideki Sugiyama
2月のキャンプ。解説者、マスコミ、ファン、あらゆる人間が松坂に殺到した。「160km出せる」という見出しが躍る。東尾は危機感を抱き、2つの禁を設けた。
スライダーを投げるな。
スピードガンを見るな。
「カーブを投げろっていうこと。あいつは肩甲骨が硬かったからそれを柔らかく使うために。それにスピードは打者の反応と自分の手応えで感じるもの。160kmでも打たれるし、140kmでも空振りは取れる。馬力だけで放っていると短命なんだよ」
多くの人が松坂に夢を抱きながらもそれが本物か幻想か、まだわからなかった頃、東尾は確信していた。だからボールを渡し、理に根ざしたレールを敷いた。これは決して夢などではなく現実の道なのだと。そのために最初の一歩が大切だと考えた。
「俺は箕島の田舎からいきなりプロに飛び込んでそのレベルの違いに自信をなくした。開幕は相手もエース級がくる。最初に軌道に乗ることが大事だから」
オーナーに背いてまで開幕から4戦目、敵地でのデビューと決めた背景にはそういう思いがあった。だから何としても勝たせなければならない。そんな不安を吹き飛ばしたのが初回、155kmのストレートだった。東尾にとってはその1球で十分だった。
空振りの後、膝をついた片岡は左ふくらはぎの筋肉に痛みを感じていた。冷静で選球眼に優れた打者がなぜ、体の限界を超えるほど強く振ったのか。
「プロ野球人生であんな空振りをしたことはない。とにかく、この投手は最初に叩いておかないと、という気持ちだった」
怪物の門出を真っ向勝負で迎える。そんな綺麗事ではない。脅威の芽は摘んでしまわなければやがて自分が舞台から去ることになる。片岡は計り知れないものを感じさせる若者を本気で潰しにいったのだ。主砲が感じたその危機感はイニングを追うごとにベンチに充満していった。そしてノーヒットで迎えた5回、フランクリンが内角高めの速球に怒り、松坂につめ寄ると両軍がベンチを飛び出した。
「心を動揺させたり、どんなことをしてでも叩かなければという空気だった」(片岡)
百戦錬磨の男たちもなりふり構っていられなかった。だが松坂は怯むどころか真っ向から睨み返し、1歩前に進み出た。
日本ハムにようやく初ヒットが出たのは6回1アウトからだった。8回2失点。圧倒的なプロ初勝利。甲子園の怪物はそのままプロでも怪物だった。夢と現実の境を忘れさせてくれる右腕に人々は熱狂した。
片岡はこの試合、4打数ノーヒットに終わった。初回の三振以降もボール球に手を出すらしくないシーンが目立った。
「あの1球を空振りしてから、最後までずっと手から力みが消えんかった……」
松坂の巨大な才能は片岡の感覚を破壊していた。ただ、あの空振りについて今、残っているのは誇らしさだけだという。
「あの後も松坂に対しては気持ちの入り方が違った。彼も必ず逃げることなく向かってきた。あのクソボールを振らなければ記憶に残ることもなかったし、彼とそういう関係にはならなかった。誇らしいよ」
東尾はその後、松坂が3年連続最多勝に輝いた01年に退任したが、それ以降も向ける眼差しは変わっていない。
2年前の8月18日、松坂から電話があった。肩の手術を受ける病院の待合室からだった。
「今から手術します」
東尾が返したのは一言だけだったという。
「気いつけえよ」
励ましも、慰めも口にはしなかった。
「日本に戻ってきた時にわかっていた。昔の大輔には戻れない。でもその当時は、言えなかった。みんな期待していたから。あいつの頭の中も昔のイメージとのギャップが大きすぎるから、どういうスタイルがいいかと考えている。昔にはもう……」
あの頃、松坂に夢を見た人たちは今もどこかでその続きを望んでいる。ただ誰より早く、その可能性を確信していた東尾は、だからこそあの日から始まった物語を最も現実的に見つめてきたのかもしれない。
今年に入り、松坂に会った東尾はこう言ったという。
「お前、200勝無理やな。俺のボール、どうするんや」
お互いに笑みを交わした。ボールの行方はまだ見えない。そもそも東尾はボールを返して欲しいと思っているのだろうか。
「実際、トロフィーなんて俺の家にはないけど、気持ちの中にあるよ。プライドだとか、自負だとか。自分の中に持っておけばいいことだから」
このボールの重みを感じてくれ――。初めて会った時に伝えた。投手の夢と現実がつまったその白球。口下手な自分に代わり、多くを語ってくれたであろう白球。今、松坂にはどれほどの重みだろうか。東尾の眼差しはその行く末をじっと見守っているようだった。