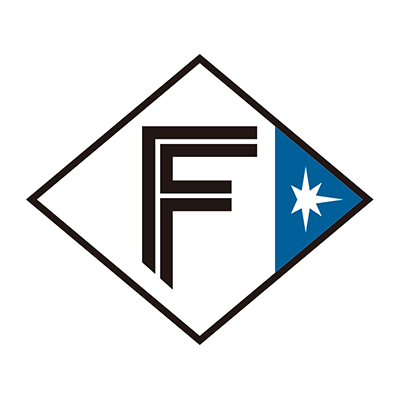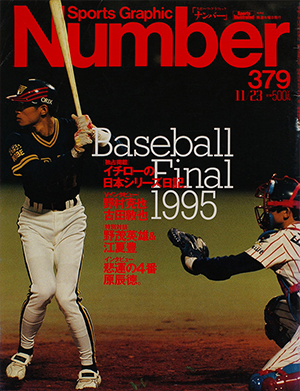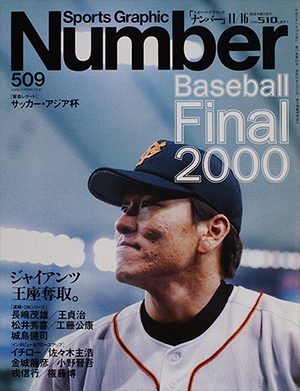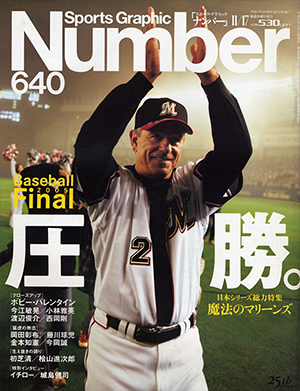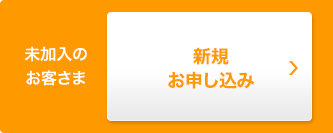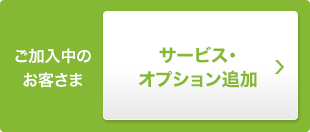創刊40周年を迎えるスポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』のバックナンバーから、
球団ごとの名試合、名シーンを書き綴った記事を復刻。2020年シーズンはどんな名勝負がみられるのか。

2004年西武 日本一
伊東勤vs.落合博満 智謀と意地と。
text by Osamu Nagatani
そして秋季キャンプ。落合の頭には〝テスト生として野球に打ち込む川相の姿を若手が見れば、きつと何かを感じ取ってくれる〟との狙いがあった。川相は当時をこう振り返る。
「若い連中と一緒にやれるならば来てくれ、と言われた。でも、テストを受けてくれよ、と言われた時には正直、〝えっ?〟と思った。でも、その意図はすぐにわかりました」
犠牲バントの世界記録を樹立した40歳の男の、野球へのひたむきさ。外野の名手として欠かせぬ戦カとなった英智も刺激を受けた。
「自分の甘さを感じた。でも、何かに秀でれば生き残れると、思えるようになった」
川相の姿を見せながら、落合は若手選手たちに時問無制限のバッティング練習を指示していた。つまり、〝プロの手本を目の前において、好きなだけ練習をやっていい、オレは見てるから〟ということ。当然若手は目の色を変えた。6年目の外野手・森章剛も〝ここでチャンスをもらえれば、一軍に定着できる〟と思ったという。
落合監督は、こう言った。
「オレはロッテに入団した時、ドラフト3位だった。誰も大して認めてくれていなかったし、〝あのフォームではダメ〟とも言われたからね。でも、プロに入ってくる以上は、必ず何かいいものを持っているはずだから、すべて自分の目で確かめたいんだ」
だから秋季キャンプでは、一・二軍の区別なしでの練習が行われた。それがそのまま今季につながっている。支配下登録選手70人のうち、56人の選手を一軍で使うことによって選手間の意識の向上が自然と図られたのだ。佐藤道郎二軍監督もこう証言する。
「監督はこっちが推薦した選手をどんどん使ってくれるので、二軍の連中はイキイキしていた。いくら結果を出しても上にあげてもらえない巨人との違いはここなんですよ」
一・二軍を分け隔てせず、チーム全体の意識を高めていくという落合監督の流儀。それは昨年の秋季キャンプの1カ月で、すでにチーム内に十分浸透していたのである。
「秋季キャンプの時期は〝戦っていない〟のだから、理想的な話はいくらでもできる。ウチの監督は、ペナントレースでも、シーズン前の方針を貫き通してくれたんです」
森繁和投手コーチがこう言うように、先発投手の起用法も〝分け隔てのない〟ものだった。しかし長峰昌司や小笠原孝ら若手が先発入りする中で、ベテランの野口茂樹は干されていた。〝ベテランでも中途半端なプライドを捨て去って一皮剥けないと若いチームには入っていけないぞ〟――。そんな信念に基づいて、川相を獲得したときとは正反対の扱いをしたのである。ちなみに今、中日が清原和博(巨人)を獲得するという噂があるが、それも川相のときと同様〝裸一貫で出直すならば〟というスタンスなのではないだろうか。
一・二軍の区別なし、については、コーチ陣についても同じ。「キャンプで決めるから」ということで、佐藤二軍監督以外はまったく白紙からのスタート。また、そのコーチの人選も実に落合監督らしいものだった。
「お前の現役時代の手首の使い方はすごかった。あれを中日の若い連中に伝えてほしい」
そう言われて、まったく縁がないのに突然コーチ就任を打診されたのが石嶺和彦打撃コーチである。石嶺に限らず、落合監督が呼んだコーチは、落合と一緒のチームにいたり、先輩後輩の関係だったり、というわけではなく、純粋に自分の目で選んでいた。また、〝選手に対して真剣に怒れるコーチ〟であることも重要だった。〝練習では選手を叱吃しながら鍛え上げるコーチがいて、試合になれば自分を活かすプレーを求める監督がいる。そのコンビネーションがあれば、選手たちは余分なことを考えずに自分の役割を果たしてくれる〟との目論見があったのだ。
荒木雅博や井端の証言も、その考えを裏付けるものである。
「今年ほど毎試合、自分の役割を考え目的意識を持ってプレーできた年はない」(荒木)
「相手のことはオレたちベンチが考えればいい、お前たちは自分のプレーをしてくれればいい、と何度言われたことか」(井端)
投手の交代時期について、ある程度の権限を任された谷繁もこう言った。
「グラウンドでプレーするこっちの意見をしっかり聞いてくれるからやりがいがあった」
落合監督の現役時代からの趣味のひとつに〝人間洞察〟というものがある。暇さえあれば、人間を観察していた。落合監督はその経験を最大限に活かす方法をとった。シーズン中も、誰が一軍コーチに適しているか、誰が二軍での若手育成に向いているかを見極め、一軍、二軍の人事を積極的に動かした。そうすることで、ベンチ内も常にフレッシュで、活気に満ちた雰囲気を保ったまま、長いペナントレースを乗り切っていったのだ。