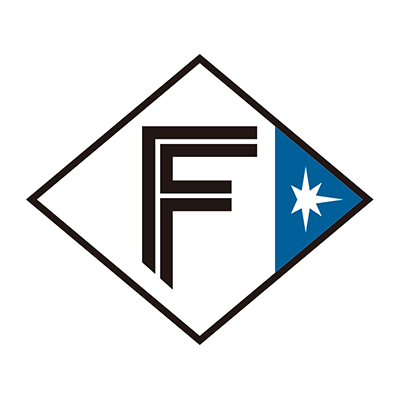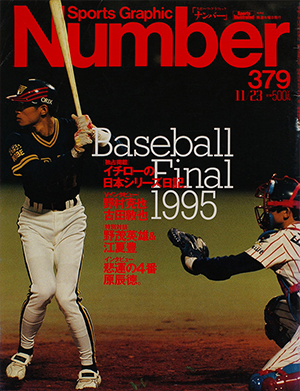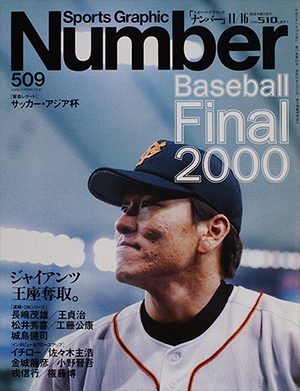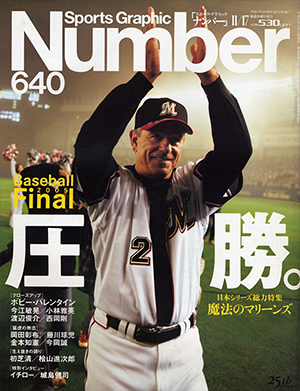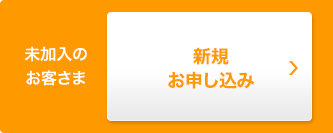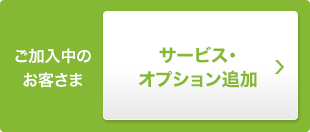創刊40周年を迎えるスポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』のバックナンバーから、
球団ごとの名試合、名シーンを書き綴った記事を復刻。2020年シーズンはどんな名勝負がみられるのか。

2016年広島 セ・リーグ優勝
From 1996 to 2016 メークドラマ〝悲劇〟をこえて。
text by Tadahira Suzuki
女手一つで育ててくれた母は当初、プロ入りに反対していた。そんな母を安心させるのが広島の勝利だった。そして、何より佐々岡とすれ違うように、壮絶に散っていった津田の魂に報いたかった。赤いユニホームのためなら、先発でも、抑えでも、いつも同じ気持ちで腕を振れた。だから、佐々岡はあの年、眠れない夜を過ごしながらも、最後までチームの命運を背負う最終回のマウンドに立ち続けた。
10月6日、巨人が優勝を果たした時、広島の選手たちは横浜で試合を終えたところだった。佐々岡は、その瞬問をテレビで見ていた。歓喜のマウンドにいたのはカープが指名し、カープが育てた左腕・川口和久だった。3年前に導入された「FA制度」が市民球団に突きつけた残酷な現実。それをじっと、目に焼き付けていた。
「胴上げを見ながら、本当に悔しかったのを覚えています。絶対に次は俺たちが逆の立場になってやるぞ、と思った。でも、結局、僕が引退するまで、その時はやってこなかった。あの時、勝っていれば、こんなに長く優勝から遠ざかることもなかったのかな、と。そういう責任も感じますね」
今、二軍投手コーチを務める佐々岡は、そう言って、遠い目をした。
今より球団格差がはっきりしていた時代、持つ者が起こした「奇跡」の裏で、持たざる者が泣いた。紀藤も、野村も、佐々岡も、その「悲劇」の主人公となった。
ただ、男たちに共通することがある。それは悔しさを口にしながらも、悔いが見あたらないことだ。あの時、もっとこうしていれば……。そういう未練がないのだ。彼らは間違いや、ミスを犯したわけではない。矢がつき、刀が折れるまで戦った末、戦場に倒れたのだ。紀藤の言葉がそれを物語る。
「ファンの方には申し訳なかったと、今でも思う。でも、みんな、今できることをやった。あれ以上のことはできなかった。それぐらい、限界まで戦った。だから、悔いはないんだよね」
あの年を境に、広島は長い、長い、トンネルに入った。15年連続Bクラスという屈辱が続いた。そんな中、あの年、チームリーダーだった野村は暗闇の時代を終わらせるべく、2010年に監督となり、菊池涼介、丸佳浩という将来のリーダーになれる逸材を抜擢した。
「優勝を逃した後、長く低迷しましたよね。それはチームリーダーがいなかったからなんです。(07年に)黒田と新井が移籍して、そういう存在がいなくなってしまった。だから、自分が監督になった時、まず、リーダーを作ろうと思いました。菊池は1つ教えたことを、すぐに吸収できる能力があった。丸は誰にもない勝負強さがあった」
野村は、かつての自分よりも、もっと強く、幹の太い柱をつくりたかった。優勝するためには、そういう男が必要だということを肌で知っていた。だから、菊池と丸にはあえて、こう告げた。
「俺はお前たちが不甲斐なければ、みんなの前で怒るぞ。期待するから怒るんだ。だから、それに負けるな」
今年9月10日、緒方は東京ドームにいた。あの96年、1番打者としてリーグ最多50盗塁を記録し、打線を引っ張り続けた男は、巨人を相手に25年ぶりの扉をこじ開けた。真っ赤に染まった敵地で宙に舞った。悲劇を知る指揮官は、それを経験したものにしかわからない胸の内を明かした。
「強い、強いと言われましたが、開幕からずっと苦しかった。正直、最後の1アウトを取るまで、信じられなかったです……」
そして、深く息を吸い込むと、あの時、ともに戦った仲間や、儚い夢を見たファンの思いも込めて、スタンドに向かって、こう叫んだ。
「全国のカープファンの皆さん、お待たせしました!」
あの年、守備固めや代打でチームを支えた高信二はヘッドコーチとして、それを見ていた。時折、目頭を押さえながら、巨人の本拠地が赤く揺れる様を見つめていた。
今シーズン、緒方と高は話し合った上でメディカルスタッフに告げたという。
「選手に怪我の予兆があれば、早めにどんどん言うように。遠慮してはいけない」
そして、選手に対しては試合のない月曜日を「休養日」とした。かつての猛練習のイメージからはかけ離れて映るが、高はスタッフからのある報告を聞いて、手応えを感じたという。
「もちろん、体を休めるための休養日ですから、休んでいいんです。ただ、スタッフが『ほとんどの選手が球場に来て、体を動かしていますよ』と教えてくれた。これは、いけるんじゃないかなと思いました」
今年7月下旬、2位巨人に11ゲーム差をつけた。あの年と酷似する状況に周囲は囃し立て、広島市民は不安を抱いた。
メークドラマの再現か――。
だが、広島は、あの時のように力尽きることはなかった。4番の新井貴浩を休ませた時には、普段はベンチに控えている松山竜平が打った。ベテラン黒田博樹が勝てない時は、若き野村祐輔が勝った。伝統を継ぎながらも、革新の一歩を踏み出した新時代の広島カープは勝者にふさわしかった。そして、その礎を築いたのは、あの年の悲劇を知る者たちだった。
20年前、力尽きて倒れた〝赤き屍〟の上に、今、歓喜の花が咲いた。