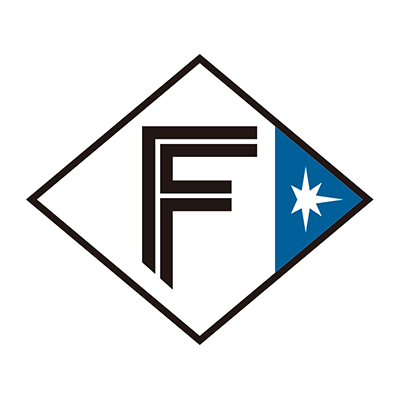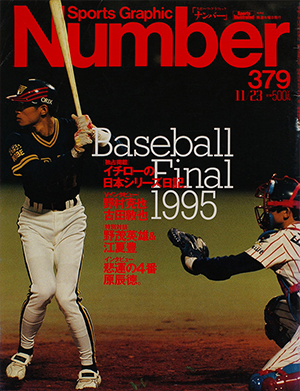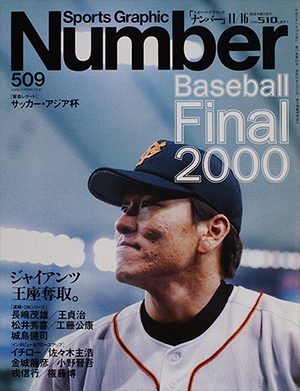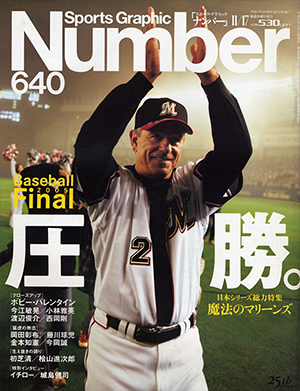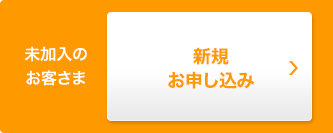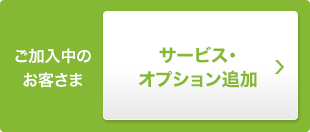創刊40周年を迎えるスポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』のバックナンバーから、
球団ごとの名試合、名シーンを書き綴った記事を復刻。2020年シーズンはどんな名勝負がみられるのか。

2016年広島 セ・リーグ優勝
From 1996 to 2016 メークドラマ〝悲劇〟をこえて。
text by Tadahira Suzuki
札幌・円山球場は雨だった。1996年7月9日、首位を走る広島は最大のライバルと目される巨人との対決を迎えた。両軍に11ゲームもの差があった。しかも、先発の紀藤真琴は、5月1日から2カ月半もの間、負け知らずの7連勝を飾っていた。すでにチーム内外で「優勝」の2文字が語られ始めていた。
ただ、そんな盛り上がりの中で、紀藤はある異変を感じていた。
「夏場に入ってからかな。体が言うことを聞かなくなってきた。選手の層が厚い巨人が下(の順位)にいるのは嫌らしかったし、追われる重圧は感じていたけど、それよりも疲れで体が動かなくなっていた」
試合が始まった。2回、2死から下位打線の連打で1点を失った。次打者は投手の斎藤雅樹。ここで攻撃を切るはずだった。ところが、右前打を許してしまうと、ここから歴史的な連打を浴びた。打ち取った当たりがことごとく野手の間に落ちた。3番松井秀喜の打球は一塁正面だったが、雨の影響なのか、イレギュラーにより、大きく跳ねてライト前に抜けていった。今もセ・リーグ記録として残る9者連続安打で7点を奪われた。そのうち8安打を浴びてマウンドを降りた紀藤の胸には、ある予感がよぎっていた。
「まだ、ゲーム差もあったし、危機感というほどではないんだけど、少し嫌な感じがした。松井(秀喜)の打球が一塁の前で大きく跳ねたり、詰まった打球が落ちたり、これは巨人に何かがついているのかな、と……」
チームもただの1敗と受け止めていた。これが後にターニングポイントと語られる試合になろうとは、この時はまだ、誰も知るよしもなかった。
紀藤が抱いた小さな予感は不安に変わり、危機感へと膨らんでいった。もともと〝爆弾〟を抱えていた肩と腰が限界を迎えた。9月の甲子園での阪神戦、普段は1錠しか飲まない痛み止めを3錠飲んで、何とか先発のマウンドに立った。だが、イニング間でベンチに戻ると、座っていることすら耐え難かった。仕方なく、味方の攻撃中はベンチの奥で横たわっていた。
「(広島の)攻撃が終わったら、教えてくれ」
そうスタッフに告げた。登板中に横たわるエース……。その悲壮な姿がチームの状況を表していた。
紀藤がプロの投手として転機を迎えたのは入団から11年目の、94年だった。阪神から投手コーチとしてやってきた山本和行に出会った。
「俺は阪神の頃からお前を見ていて、こうしたら、良くなるんじゃないかと思っている部分がある。どうだ、やってみるか?」
命令でも、押しつけでもない。1人のプロとして扱ってくれたことがうれしかった。
「やってみます!」
山本が教えてくれたのは、ひたすらメカニカルだった。人間の体は毎日、状態が違う。だから、投手が正しいフォームで投げるためには日々、修正を施さなければならない。その年、紀藤は16勝を挙げた。シーズン中、毎日、〝鏡〟となってくれたのが山本だった。左足を上げてから、リリースまで。自分でも気づかない部分のズレを指摘してくれた。翌年も10勝を挙げた。2年連続2桁勝利で、96年にはエースとなっていた。ただ、この年が、それまでと違っていたのは山本が退団していたことだった。
「腰が痛いから、背中を反ることができない。すると、体が早く開いてしまう。まっすぐはシュート回転するし、変化球も早く曲がってしまう。わかってはいるんだけど、自分では修正できなかった……」
持ち味の外角への制球がままならない。優勝争いの中で、思うようにならないフォームを修正しようにも、自分を正しく映してくれる〝鏡〟がなかった。
また、紀藤には初めて2桁勝利を挙げた年から、ずっと続けていた〝儀式〟があった。登板当日、早朝に起きて散歩に出かける。そして、その日、対戦する相手の1番から9番打者までをイメージして、シャドーピッチングをする。遠征先ではホテル近くの目立たない場所でやった。通勤途中の人に奇異の目で見られることもあったが、何があっても欠かさなかった。しかし、そんな心の拠り所になっていた儀式さえ、この年の夏場にはできなくなっていた。
8月以降、紀藤は勝てなくなった。9月には5試合連続KOを食らった。それでもマウンドに立ち続けた。
「プロだから相手に負けるのは仕方ない。でも、自分にだけは負けてはいけない。カープにはそういう伝統があるでしょ。衣笠さんが骨折してもフルスイングして、津田さんが病気を抱えながら、『頭が痛い』と言いながら投げていたのを知っている。『無理です』なんて、言えなかった」
そして、代わりにエースを務める投手は、この時の広島にはいなかった。
野村謙二郎はあのシーズンを振り返る時、悔しさと痛みを同時に思い出す。7月6日、神宮でのヤクルト戦で盗塁した。二塁へ滑り込んだ際、左足に激痛が走った。立ち上がれず、そのまま担架に乗せられて、退場した。
「足が……、足首が逆向いてるぞ!」
スタッフの叫びが聞こえた。球場から病院へと運ばれる救急車の中で野村は思った。
「骨が折れていて、ギプス固定しないといけないようなら、終わりだな……」
この年、広島打線は「ビッグレッドマシン」と異名を取った。緒方孝市、正田耕三、野村、江藤智、前田智徳、ロペス、金本知憲と、俊足好打に長打力まで兼ね備えた選手がズラッと並んでいた。中でも、中心が野村だった。91年のリーグ優勝を経験した男は3番遊撃手として、精神的支柱でもあった。首位を走る夏場に、離脱するわけにはいかない。その一心だった。
レントゲンを撮った後、医師に別室へと呼ばれた。この時、野村は心の底で叫んでいたという。
「先生、頼むから、骨折と言わないでくれ!と。それだけでした」
剥離骨折だった。普通ならプレーはできない。ただ、野村はそれを聞いて、胸をなでおろした。球団には「捻挫」と発表してもらった。3試合を欠場しただけで、戦列に復帰した。痛み止めを打ち、テーピングをぐるぐる巻きにして、グラウンドに立ち続けた。
それでも、相手の「傷」を見つければ、そこを徹底的に攻めるのがプロの世界だ。手負いの野村は徐々に成績を落としていった。それに伴って、チームも急降下していった。広沢克己や、落合博満が離脱しても、勢いを増していった巨人とは圧倒的に球団としての「体力」が違った。