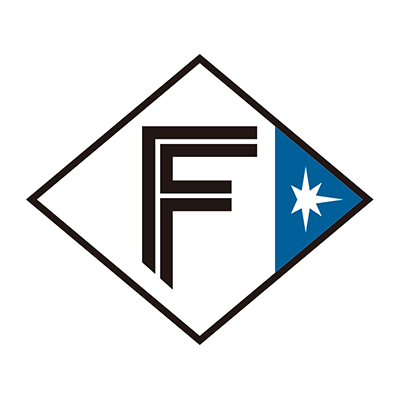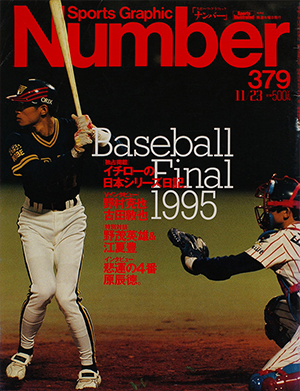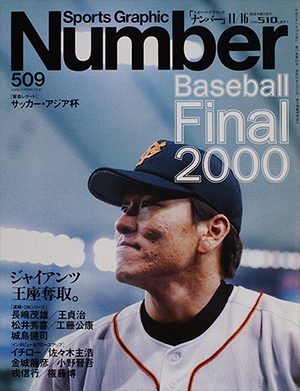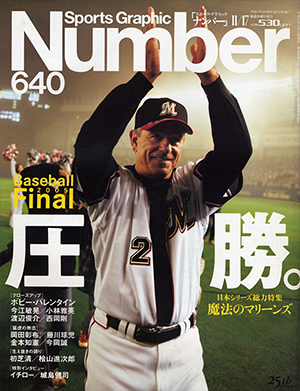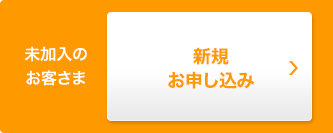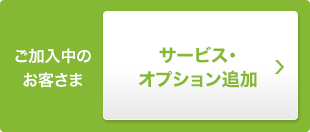創刊40周年を迎えるスポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』のバックナンバーから、
球団ごとの名試合、名シーンを書き綴った記事を復刻。2020年シーズンはどんな名勝負がみられるのか。

1995年ヤクルト 日本一
[野村IDの最高機密を独占公開]
丸裸にされていたイチロー。
text by Yuta Ishida
実際、マスコミを利用して意識の中に内角攻めをすり込ませるために、再三、イチローを挑発した。日く「イチローを攻めるには、内角に始まり内角に終わる。いかにインハイを攻め切れるか」。日く「バッターボックスから足が出とるんと違うか。完全に出たらアウトか」。イチローが打席に立つまでに、野村監督はこれだけの下準備をしていた。
その成果はどうだったのか。例えば第1戦でのブロスは、イチローの第1打席ですでに2つの有効な球を試している。①の<高めのボールゾーンの速い球>と③の<内角の速い変化>。ボールゾーンの速い球を試すには、ブロスの速球がべターだと、第1戦に持ってきた野村監督。そして、古田はすぐに手応えをつかんだ。ダイエーの工藤公康は、「イチローはバットコントロールが巧いからローボールヒッターのように思われるけど、本当は高めが好きなんだ。少しくらいのボール球でも、高めには手を出してくる」と話していたが、実際、<アソボウズ>のデータでもその傾向は明らかに出ていた。高めのボールゾーンでのファウルがかなり多く、空振りも目立っていた。また、打球方向でも、センターの真正面には飛ばない、レフトへの打球はスライドする、というデータから左中間を大きくあけ、逆に右への強いゴロが多いために一塁手と二塁手は、かなり狭く守った、など、データによる極端なシフトも敷いていた。
古田は、イチローに対しては、見事なまでに時をみて、人を見たリードをしていた。各投手に要求したパターンは、タイプによってはっきり異なっている。①の速い直球を持つブロス、川崎には高めの直球。ブロスには③の速い変化球も効果的にはさむ。変化球のコントロールのいい伊東には、②と④の内外角の低めの変化球で攻めさせる。高津には①の直球と、④の低めの変化球。吉井には①の直球を見せ球にして、③と④の変化球で勝負させた。石井と山部の両左腕にはインハイを意識させて、②の外角低めの変化球を使った。
この攻め方は、神戸で優勝を賭けたロッテ戦で、このシステムを使っていたロッテの伊良部や小宮山が使った配球と同じだった。伊良部は150kmの外角高めの直球で、イチローを空振り三振に斬って取った。これはブロスのパターンと同じである。また、今季イチローを.182に封じた小宮山は、内角の速い球でカウントを稼いで、最後は外角低めのボール球で2連続空振り三振を奪ったが、これは伊東の配球パターンと共通していた。
また野村監督は、イチローが、緩い変化球に限り初球を見逃す傾向にも着目していた。この球は、続けると危険度が高まるのだが、ワンストライクを取るのには有効で、実際に川崎や高津はこのパターンで成功している。
結局、図Aでもわかるように高めは直球、低めは変化球――裏返せば、高めには緩い変化球を絶対に投げさせない、低めのストライクを直球では取りにいかないという、イチローのデータに基づいた古田の配球には、明らかな意図があった。
このシリーズ、イチローが大事な場面で抑えられたのは、彼が<インハイの幻影>によって崩れた結果、ヤクルトが掴んでいた弱点を、はっきり露呈してしまった結果なのである。ではイチローはどこが崩れていたのか。
まず、内角高めを意識したイチローは、ミートした時に、しっかり両腕を伸ばせるように、ややカカトよりに体重を乗せた。さらにイチローは振り子を小さくして早くボールを見極め、内角高めにも対処しようと考えた。しかしその方法に工藤公康はクビを捻った。
「振り子を小さくすると、いつものタイミングよりも、踏み込む足の着地が早くなる。そうすると、タイミングに合わせるために一瞬足が止まり、その時右肩がパッと開く」。イチローは左足から右足へ軸を移動させて打つが、その時、右肩が開かないから、バットのヘツドが残ったままでインパクトの瞬間、強いスイングができる。それが、足が止まり、右肩が開き、ヘツドは残らない、では、強い打球が飛ばないのも当然だった。
天才打者は、目に見えない幻影と、目に見えた弱点を突かれて敗れた。データは確かにイチローの弱点をいくつも指し示していた。オリックスはヤクルトの繊密なデータ分析によって、サインも配球も解読きれ、長所も弱点も知り尽くされていた。しかしそれはデータを集めるシステムと、データを解析できるノウハウがうまく噛み合った結果である。片山は、データが日本シリーズで重用されたことについて、こう言った。
「卑怯だと言う人もいるかもしれないが、勝つためにはデータは大切な道具になる。道具は、使う人間がいて初めて役に立つ。データがあってもそれを分析できて、選手に伝えられて、それをグラウンドで生かせるだけのレベルの高いチームは少ない。それがヤクルト、いや、野村監督だったのかな――」