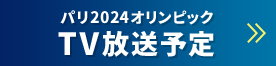2022年1月28日(金)更新
レジェンド葛西紀明のジャンプ人生
長野の屈辱バネにソチ最年長メダル

スポーツ界に「レジェンド」と呼ばれるアスリートはたくさんいますが、「リアル・レジェンド」となると、この選手にとどめを刺します。そう思わせるのが、今もノルディックスキー・ジャンプの第一線で活躍する49歳の葛西紀明選手です。
ムササビのような飛型
葛西選手は1992年アルベールビル、94年リレハンメル、98年長野、2002年ソルトレイクシティ、06年トリノ、10年バンクーバー、14年ソチ、18年平昌と8大会連続で冬季オリンピックに出場している“生ける伝説”です。94年リレハンメル大会団体銀、14年ソチ大会ラージヒル個人銀、団体銅と3個のメダルを胸に飾っています。
3個のメダルの中でも、特に印象に残っているのが41歳256日で銀を獲得した14年ソチ大会の個人ラージヒルです。これは五輪のジャンプ史上、最年長のメダルでもありました。
葛西選手は1回目139メートル、2回目133.5メートル。飛型点と合わせ合計277.4点。表彰台の真ん中に立ったポーランドのカミル・ストッフ選手とは、わずか1.3点差でした。2本の飛距離ではストッフ選手を1メートル上回っていただけに、本人によると「6対4で悔しい」銀メダルとなりました。
ソチでの葛西選手の空中姿勢の美しさは、見ていてうっとりするほどでした。低い飛び出しから両足を大きく開き、まるでムササビのように風を切る。両手は指まで開いて風を鷲掴みしていました。
40歳を過ぎて、なぜ、これほどのジャンプができるのか。長野大会個人ラージヒル、団体金メダリスト船木和喜選手の解説が参考になりました。
<踏み切りで上半身を使わないため、スキーと上半身の位置が最初から近い。ここから前傾を深めていくため、他の選手と比べてスキーと体の位置が近く、スキーのぶれにつながる横風の影響を受けない>(「スポーツニッポン」14年2月17日付)
葛西選手を長年に渡って指導してきた佐々木敏さん(元全日本スキー連盟ジャンプトレーニングドクター)は自らの著書『葛西紀明 40歳を過ぎても衰えない人の秘密』(詩想社新書)で、別の観点から、ソチで金メダルに迫った秘密を解き明かしています。
笑顔のジャンプ
<笑顔が自然と溢れるチーム、選手はいい結果を不思議と残します。逆に、笑顔がなく、しかめっ面をしているような雰囲気では、結果もついてきません。何か障害にぶつかったときに、どんどんマイナスの方向に落ちていってしまうからかもしれません。
ソチオリンピックでは、葛西は競技前から終始、心からの笑顔を見せていました。この笑顔が勝利を運んできたのだと思います。
葛西は、自分のやってきたことに間違いはない、あとはジャンプするだけだというところに自分を追い込み、迷いなく本番を迎えることができたのでしょう>
確かに、ソチでの葛西選手は終始笑顔でした。逆に言えば、この笑顔をつくるまでに、どれだけの歳月を要したのか。それを考えると、胸が熱くなってきました。
光と影。忘れられないのが98年長野大会での屈辱です。葛西選手は本番前に足を捻挫してしまい、出場は個人ノーマルヒルのみで、個人ラージヒル、そして金メダルが期待された団体には出場できませんでした。
佐々木さんによると<葛西の捻挫は完治と言える状態ではなく、ノーマルヒルに出場できただけでも喜ばなければいけない状況>(同前)だったと言います。
半分はジョークも含まれているのでしょうが、白馬のジャンプ台で原田雅彦選手が踏み切った瞬間、「落ちろ!」と叫んだのは有名な話です。
葛西選手にとって、原田選手は北海道の東海大第四高(現・東海大付札幌高)の4学年先輩です。その先輩に向かって「落ちろ!」と叫ぶのですから、自らが晴れ舞台に立てない悔しさは生半可なものではなかったのでしょう。
それについて原田選手に聞くと、こんな感想が返ってきました。「もしリレハンメルで僕が普通に飛んでいれば、僕も彼も金メダリストだった。彼のその後の人生も変わっていたものになっていたでしょう。だから長野で金メダルを獲った時、僕は真っ先に(リレハンメルの団体メンバーだった)西方仁也と葛西の顔を思い浮かべました」
誰よりも遠く、誰よりも長く――。葛西選手にとってのジャンプという競技は、彼の人生そのものなのかもしれません。

二宮清純
関連コラム
データが取得できませんでした